
数字では見えない“本当のニーズ”を知る──ビジネスに効く『エスノグラフィ研修』レポ
「エスノグラフィ」という言葉を耳にしたことはあるけれど、詳しくは知らないという方は多いのではないでしょうか。
エスノグラフィ(Ethnography)とは文化人類学の調査手法で、人々の暮らしや行動を観察し、背景にある価値観や意味を読み解くためのアプローチ。
統計やアンケートでは見えづらい「なぜこの行動をするのか」「本人も気づいていない前提とは?」といった深層にアプローチできる点から、顧客理解や新規事業開発にも応用できる手法として、ビジネスの現場でも注目されています。
このブログでは、そのエスノグラフィをビジネスで活用するためのヒントをお伝えします。
20年振りの“再会”。エスノグラフィを体感する研修へ
先日、大阪大学フォーサイト株式会社が企業向けに提供している、2日間の「エスノグラフィ研修」に参加してきました。
現在はライターとして活動している私ですが、約20年前はメーカーで消費者定性調査を担当していました。
そこで「エスノグラフィ」という言葉に出合い、大変興味を持ったものの、その仕事から離れることになり、それきりだったのです。
縁あってフォーサイト社にお声がけいただき、企業様のご厚意により参加できることになった今回の研修は、そんな私にとっては20年越しの「再会」でもありました。
「出会った瞬間から気になっていたけれど、深く知る前に疎遠になってしまった魅力的な人と再会してしまった気持ち」と言ったら伝わるでしょうか?
そんな「エスノグラフィ」に2日間どっぷり浸かったレポートを書きたいと思います。
アカデミックな学びが、現場で生きる視点をくれる
森田敦郞先生(大阪大学大学院 人間科学研究科教授)、神崎隼人先生(大阪大学附属図書館 研究開発室 特任研究員)というアカデミックな立場の先生たちによる講義では、「エスノグラフィとは何か」「なぜ今、企業に必要なのか」を教えていただきました。
まず印象に残ったのは、「現実は自分の想像力の枠を超える」という表現。
この言葉を聞いて、私はこれまで、「(特にビジネスにおいては)数字を元に、論理的に考えたことが正しい」と思い込んでいたことに気づいたんですよね。
数字は大切です。でも、現場にはもっと多くの、生の、そして大切な情報が溢れているのです。
それを見ずに、数字ばっかりを追いかけている人、多いんじゃないかな……。
文化人類学というフィールドワークを通して他者の世界を理解しようとする学問が、「頭脳」を過度に信じるようになった私たちに、警笛を鳴らしているように感じました。
また、
「リサーチャーはクセや特性のある“全身計測器”であり、その捉え方の違いに価値がある」という表現にも心が震えました。
このエスノグラフィの考え方は、私がこのAI時代に感じていたモヤモヤを吹き飛ばしてくれるものでした。
一人ひとりが、自分のアンテナを信じて現実を観察し、調査データを得るーそれをビジネスにつなげることができるとしたら……すごくワクワクしませんか?
それは、AI時代に求められる、「人間にしかできないこと」だと思うのです。
この視点を携えて、講義のあとは実践に移りました。
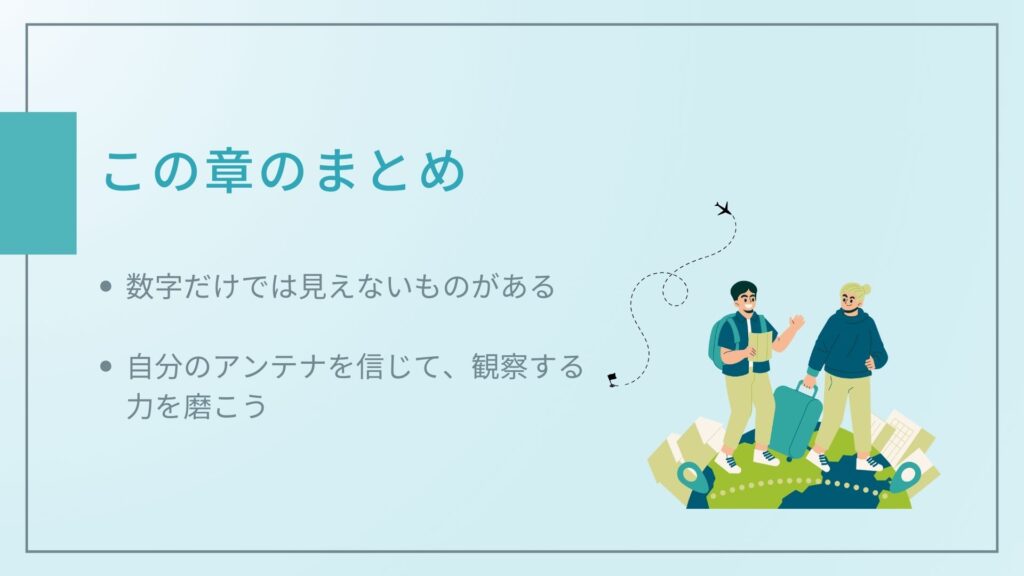
現場に入り、感じて、書き留める──フィールドワーク体験
少人数のチームに分かれて、短い時間でしたが実際に「参与観察」を行いました。
企業が提供しているものに近いサービスの現場に出向いて、観察をするというこのフィールドワーク。
遠巻きに状況を観察するグループもあれば、自分が当事者として場に入り込むグループもありました。
観察したことを詳細に書き留めたフィールドノートをメンバー同士で読みあうと、同じ場にいても、注目するポイントや記述する言葉が全然違うことを思い知ったのです。
自分が全くスルーしていた事実に着目している仲間や、同じものを見てもまったく異なる表現をする仲間を見て、その違いに驚きました。
「この人は俯瞰して全体を捉えるのが得意なんだな」
「自分の感じたことにぐっと潜り込むタイプだったんだ」
「こんな詩的な表現をする人だったんだ」
そんな発見は、調査結果の共有にとどまらない価値がある、と私は感じました。
対象のサービスについて、多角的な気づきが生まれるだけでなく、チームメンバーの“感性の違い”に触れることができるのです。
ビジネスにおいて、チームメンバーの特性や思考のクセを知ることは、意思疎通や役割分担に直結します。
エスノグラフィというツールを用いることは、そんな「チームメンバーの相互理解」という観点からも、とてもプラスに働くように感じました。
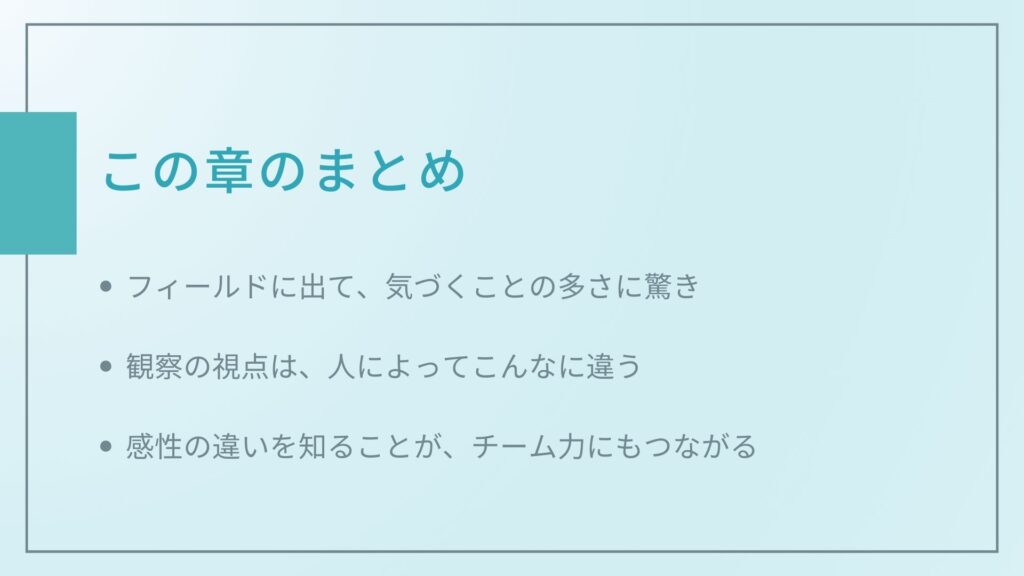
「自分だから気づけたこと」が、データになる
その後、フィールドノートに書き留めた言葉をもとに「コーディング(言語の整理・抽象化)」を行いました。
これは、質的調査で陥りがちな「独りよがりな感想」で終わらせず、意味のある調査データにするために重要なステップです。
「コーディング」と聞くと、テキストマイニングのように、テキストデータから、意味のある情報や傾向を自動的に抽出するような印象を受けますが、そうではありません。
元の文脈に戻れるような意識で、「現場の言葉(具体)」を「理論の言葉(抽象)」へと置き換えていくのです。
(これが結構難しく、苦労している方も多かった!)
自分の個人的な感情や主観のように感じていたものが、意味のある“質的データ”へと昇華していく過程は、私にとって大変刺激的な体験でした。
「ただの個人的な気づきなので」と謙遜してしまいそうなことが、ビジネスの大きなヒントへと育つ可能性があること……ぜひたくさんの人に知ってほしいと思いました。
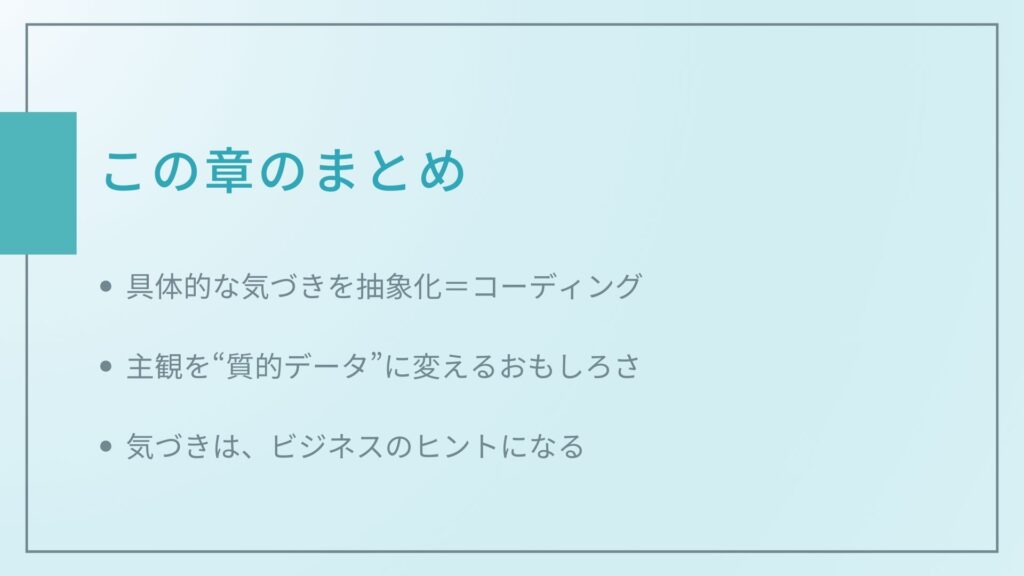
統計だけじゃ足りない時代に、「人間を見る力」を
この研修で得たのは、「エスノグラフィをビジネスに活かすにはどうしたらよいか?」という知識だけでなく、実際にやってみることではじめて分かる“身体感覚”でした。
「現場で何が起こっているかをよく見ること」「自分が感じたことを大切にすること」──それは、数字ではすくいきれない、人間の本質に向きあうために必要なことです。
先の見えない今の時代のビジネスには、小手先のテクニックではなく、人間の本質的な部分をつかみ取る必要があるように思います。
そういった意味で、人文知の分野における「人の本質を探る研究」は、ビジネスにも通じるものがあるのですよね。
寺山修司は約90年前に「書を捨てよ、町へ出よう」と言いましたが、まさに今、統計的データを軸としたビジネスに行き詰まっている方は、「パソコンを閉じよ、町へ出よう」ですね。
顧客理解に悩んでいる方、新しい事業を考えている方、チームの多様性を力に変えたい方にとって、エスノグラフィは確かなヒントになると感じました。
2日間の研修を受け、20年振りの人に再会して、「やっぱり私が思ったとおり、素敵な人だった」とホクホクしているかのような感覚です。
エスノグラフィ、奥が深い……。もっともっと知りたくなりました。
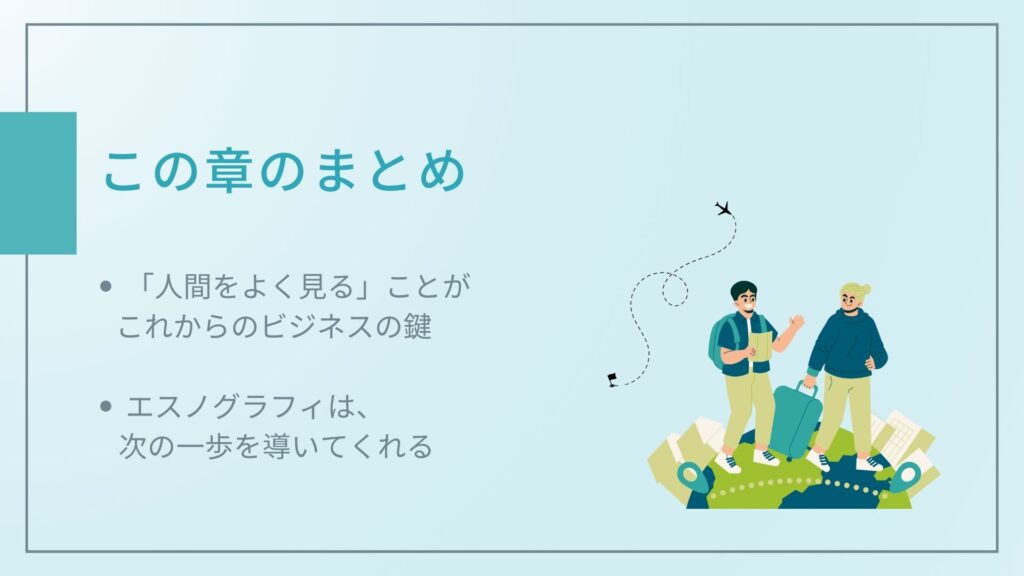
エスノグラフィ研修に興味を持たれた方は、大阪大学フォーサイト(株)までお問い合わせを。


